横須賀で初めての講演会 「三浦半島の往還と”海道”」のレジュメを公開します

横須賀市史は、2000年度から2012年度まで近世部会の専門委員を務めていました。最後の年は、甲状腺眼症という病気にかかって3週間ほど入院し、その後、2回目の手術をしましたので、何とも受難の年でした。そうした中で、今回、NPO法人よこすかシティ協会からのお招きを受けまして、「三浦半島の往還と“海道“」と題する講演を行ないました。といっても、2月の16日のことですからもう2週間近く経ってしまいましたね。そもそも横須賀に行くこと自体が久しぶりのことでした。恐らく5年ぶりぐらいだったでしょうか?




往還はこの場合、東海道をはじめとする五街道に対する脇往還、脇街道のことです。五街道は人や物を運ぶ際に宿駅(宿場)ごとに人足と馬を乗り継ぎます。これを伝馬役といい、人馬が不足した場合は、周辺の村落から補給します。これを助郷役といいます。脇往還にも同じような機能を持った村が指定されていて、これを継立場といいます。もちろん、宿駅に比べればずっと小さいのですが、場所によっては助郷役に相当するものも設定されています。とくに下田(静岡県下田市)から浦賀に番所が移転してからは、浦賀にいたる往還と三崎(神奈川県三崎市)にいたる往還にはもちろん継立場が設定されているのですが、同時にすべての継立場に助郷役が設定されています。また、浦賀周辺の村には継立場助郷役は設定されていませんが、その代わり、浦賀奉行所の御用船に関する水主役(かこやく)が設定されていました。これらについては、相州三浦郡の継立人馬役・水主役と日光社参人馬役と題する論文にしていまして、「馬場研究室へようこそ」のコーナでダウンロードできますので、興味のある方は是非ご覧ください(http://www.ihmlab.net/tweet/babalab/)。
”海道”は、海の道、この場合は浦と浦を結ぶ渡船場の意味で使っています。往還と渡船場が有機的に連携することで、半島は行き止まりではなく、海に向かって開けていくまさに”海道”の役割を話しているというわけです。そして、こうした三浦半島の往還に関する役は、時代が降るにしたがって、金沢町屋村(横浜市金沢区)や鎌倉雪之下村(鎌倉市)の継立役も負担するようになっていきます。そして海防の負担が厳しくなるにつれて、さらには幕末の騒乱の中で次第に東海道の宿場町への負担にも巻き込まれていきます。そんなこんなについてお話ししました。
「三浦半島の往還と”海道”」レジュメ=yokosuka_kouen
投稿者プロフィール

最新の投稿
 今日のつぶやき2023年10月2日一炊の夢 L188Mile
今日のつぶやき2023年10月2日一炊の夢 L188Mile お知らせ2023年9月12日秋の北條秀司展 L257Mile
お知らせ2023年9月12日秋の北條秀司展 L257Mile 今日のつぶやき2023年6月29日夏色 L281Mile
今日のつぶやき2023年6月29日夏色 L281Mile 今日のつぶやき2023年6月21日あつぎ郷土博物館 L289Mile
今日のつぶやき2023年6月21日あつぎ郷土博物館 L289Mile
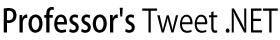






コメントを残す